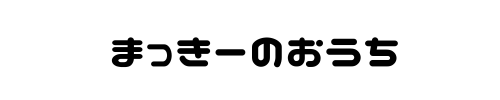バイクは車より事故での怪我が多いです。4輪とは違って2輪はバランスも悪いですし止まってしまうと倒れてしまいます。全身むき出しになっているので、転んだ時や追突されたときは投げ出されたりして大けがしてしまうので、どうしても身を守ることが必須です。
皆さんはバイクに乗るときに対策はしていますか?
プロテクターがあるとないとでは身体に対してのダメージが違います。安全に乗るためには、必要なものであることには間違いないです。
今回はバイクジャケット、胸部のプロテクターの事を伝えていきたいと思います。
これ記事を見たら
がわかると思います。
損傷による死亡率の軽減
バイクジャケットは「デザイン」よりも「安全性」が大事です。特にプロテクター付きジャケットは、万が一の事故で体を守ってくれるライダー必須の装備といえます。あるとないとでは事故の時の死亡の確率が大幅に軽減します。
バイクは車と違って、転倒したときに体がむき出しになります。肩や肘、背中は特にダメージを受けやすく、骨折や後遺症につながることも少なくありません。プロテクターは衝撃を分散・吸収してケガを最小限に抑えてくれるため、着ているかどうかで大きな差が出ます。
追突したとき、ハンドルや壁、車にぶつかるときに胸を強打して亡くなる方が多く、頭に次いで2位の損傷による死亡につながる箇所なのです。最近は軽量化や通気性が進化しており、暑い夏でも使いやすいモデルが増えてきました。
導入のきっかけ
僕自身、バイクに乗り始めた頃は特に安全性を意識していたことは本当にありませんでした。Tシャツで乗っていたり、半ヘルメットなどで乗っていました。冬の間もダウンジャケットで乗っていてバタバタとなびかせていました。何年かした時にバイクに乗る時に適したものはないのかなと思っていると、ナップスでゴールドウインの冬用のジャケットを見つけてから購入、ずっと使っています。今でも使ってます。ちょっとした肘と背中のプロテクターが入っているものです。
プロテクターなしのダウンジャケットを使っていたときに東京から福井までツーリング、11月でしたけど寒いのをいまだに覚えています。インカムもないときに友達と夜中も走り寒かったですね。山奥でパナウェーブの集団にもあったりしたりと楽しい思い出です。
最近よくニュースで胸を打って重体とか、追突した反動でハンドルに胸を強打と聞いたりするとゾッとします。それから、プロテクター付きジャケットの大切さを思いました。
種類はどのようなものがある?
バイク用胸部プロテクターには、装着方法や形状によっていくつかの種類があり、それぞれ安全性や使い勝手が異なります。そして、その安全性を測る重要な基準として「CE規格」があります。CE規格については後で説明しています。
1. バイク用胸部プロテクターの種類
主に以下の3つのタイプに分けられます。
① ジャケット内蔵型
ライディングジャケットのポケットにあらかじめプロテクターが内蔵されているか、後から挿入できるようになっているタイプです。こちらはセパレートタイプでもあります。
- 特徴: ジャケットと一体になっているため、装着の手間が少なく、見た目もスッキリしています。
- メリット:
- 手軽さ: 着脱が簡単で、プロテクターを別で持ち運ぶ必要がありません。
- 見た目: アウターに響かず、普段着に近いスタイルでバイクに乗りたい人に向いています。
- デメリット:
- フィット感: プロテクターがジャケットの中に内蔵してあり、大きさも胸の一部分で衝撃時に最適な位置で守ってくれない可能性があります。
- 防御力: 一部の製品は比較的柔らかい素材が使われているため、単体プロテクターに比べて衝撃吸収性が劣る場合があります。別売りで交換できるものもあります。
② ベスト・インナー・単体型
ジャケットの下に、ベストやインナーのように単体で着用するタイプです。
- 特徴: プロテクターが体に直接フィットするため、事故時のズレを最小限に抑えられます。背中も一緒に守れるものがある。
- メリット:
- 高い防御力: 衝撃を確実に吸収できるよう、硬質な素材(ハードタイプ)や、衝撃を受けると硬化する特殊な素材(ソフトタイプ)が使われていることが多いです。
- 汎用性: どのジャケットを着る時でも、これ一枚を着ればプロテクションを確保できます。防御できる部分が大きいものが多い。好きな服が着れる。
- デメリット:
- 手間: ジャケットとは別に、もう一枚着る手間がかかります。
- かさばり感: 素材によっては厚みがあり、着ぶくれしたり、動きが制限されたりする場合があります。
③ セパレート・一体型
単体で使うプロテクターの中でも、形状によって「セパレートタイプ」と「一体型(フルチェスト)」に分かれます。
- セパレートタイプ: 左右の胸部が分かれているタイプです。
- メリット: 体の動きに柔軟に対応し、胸を張り出したライディングポジションでも窮屈さを感じにくいです。
- デメリット:単体型と同じようにかさばる。
 | RSタイチ(アールエスタイチ) TRV079 HELINX セパレート チェストプロテクター MEN'S胸部プロテクター バイク プロテクター 価格:7800円 |
- 一体型: 左右の胸部が繋がった、一枚の板のようなタイプです。
- メリット: 衝撃が左右の胸部に広く分散されるため、セパレート型より高い防御力を持つとされています。
 | コミネ プロテクター SK-828 エアスルーCE レベル2ボディアーマーフィット KOMINE 04-828 CE規格認証 価格:9879円 |
- 通勤・通学ライダー:毎日乗るからこそ、ちょっとした転倒のリスクに備えられる
- ツーリング好き:長距離で疲れて注意力が落ちても安心感がある
- 初心者ライダー:運転に慣れるまで転倒リスクが高いため、まずは安全重視
- スポーツ走行や峠好き:スピードが出る場面では、ハイグレードなプロテクターが安心
プロテクター付きジャケットは「安全性を買う」という考え方で選ぶと、きっと後悔しません。
エアバッグというのもありますがこちらは一回使うとボンベを買いなおしたりしないといけないので、常時使うのにはちょっと難しいのかなと思っています。ただ安全性は高いです。
2. 安全基準について
① CE規格
ヨーロッパの安全基準であり、バイク用胸部プロテクターの安全性を示す最も重要な指標です。
- テスト内容: 質量5kgの重りを1mの高さから落下させ、プロテクターを通して体に伝わる衝撃の力(kN/キロニュートン)を測定します。
- レベルと基準値:
- レベル1: 平均衝撃力が30kN以下、最大衝撃力が45kN以下であること。
- レベル2: 平均衝撃力が20kN以下、最大衝撃力が35kN以下であること。
| 規格レベル | 性能の目安 | 選び方のポイント |
| Level 1 (CE1) | 標準的な衝撃吸収能力。 衝撃を体へ伝わる力を一定値以下に抑えます。 | 軽さや動きやすさ重視の**関節部(肘、膝、肩)**に向いています。 |
| Level 2 (CE2) | 最高水準の衝撃吸収能力。 Level 1より身体に伝える力が少ない。 | 致命傷につながる胸部・脊髄には、できる限りLevel 2を選ぶことが推奨されます。 |
結論として、CE規格のレベル2のほうがより厳しい基準をクリアしており、高い衝撃吸収性能を持っていると言えます。
② 日本国内の安全基準
現在のところ、ヘルメットのように法律で定められたプロテクターの安全基準はありません。
しかし、**「全国二輪車用品連合会(JMCA)」が、CE規格を準拠した製品を「JMCA胸部プロテクター推奨」**として認定する取り組みを行っており、プロテクター選びの一つの目安になっています。
どのプロテクターを持っていればよいか
プロテクター入りのジャケットを春夏秋用3シーズン用、冬用をそれぞれ1着ずつあればとりあえず良いと思います。バイクに乗るときはジャケットを着ていれば、一応プロテクターがついているので大丈夫。ですが、ちょっとした買い物や、友達と遊びに行くときはジャケットだとバイク乗りを強調してしまうので躊躇してしまうと思います。
そのような方はベスト型の一体式がお勧めです。
乗っている時だけ着用し、バイクを降りたら、ワイヤーでバイクに括り付けておけます。歩きとかも邪魔にならないです。ただちょっと重くかさばるのが難点です。


自分はこれを使っていて夏も冬も使っています。強度もしっかりしていて取り外しも簡単なので気に入っています。ちょっと重いのが難点ですが、長時間ツーリングみたいに使うわけではないし、安全には変えられないと思っています。夏はTシャツの上から、冬はアウターの下に着ています。
間違いない選び方
CE規格に準じている物であれば問題ないと思います。ジャケット内蔵型であれば、プロテクターの厚さ分、出てしまうのでサイズ選びは慎重にしましょう。体が大きい人はワンサイズ大きめのジャケットでもよいかもしれないですね。
インナーなどの物はシャツの上に着たりしますので、トレーナーとかのサイズ選びと同じようにしてもよいですね。インナータイプは長く使っていると生地が伸びたりして、胸の部分からずれたりすることがあるので伸びたら交換をする、そのような感じになります。
僕の使っている物はベルクロでサイズを変えられるので、体に合わせて調整できるところがよいですね。分厚いので動きはインナータイプに比べると動きづらいですが、安心感は全然違います。背中もしっかりと守ってくれるので。時期によってアウターの中に仕込むのか、又は、シャツの上に着用していくのかを選べます。
ハードタイプは、硬いタイプは安心感はありますが動きにくい印象です。
ソフトタイプは、柔らかいのはスポンジが多いので安全性が少し足りないように感じてしまいます。
最近は、はじめは柔らかいのですが衝撃を受けると瞬間的に硬くなるという素材を使ったものが出てきました。ただ値段がその分高くなってしまうので、予算が取れれば選んでみてもよいかと思います。メーカーによって名前が違いますが、安全基準は変わらないので安心してください。初めは柔らかいもので、高速道路を走ったりしてもう少し安全性を確保したいのであればCE2規格の物に入れ替えるということもできます。
初めは柔らかくて、衝撃を受けると急に硬くなる(あるいは硬さが増す)性質を持つ素材は、「レオロジー特性(粘弾性、せん断増粘= shear thickening)」を利用した保護材料として知られています。バイク用プロテクターにもこの種の素材を使ったものが増えています。
以下、代表的な素材と、それを使っているメーカー/製品例を挙げます。
| メーカー/ブランド | 採用素材/技術 | コメント |
| RSタイチ (RS Taichi) | TECCELL(ハニカム構造素材) | RSタイチの “TECCELL Chest Protector” が実際に市場に出ている例がある。RS-TAICHI |
| Daytona (日本ブランド) | SAS-TEC | 上記例で “DAYTONA SAS-TEC 胸部プロテクター” 製品が複数ある。 |
| RHEON Labs / 製品ブランド | RHEON™ | 最新の素材技術で、柔軟性+衝撃硬化性を持つ新世代アーマー素材として紹介されている。 |
| 汎用ブランド・アーマーメーカー | D3O® | 多くのアーマー(胸・背中・関節部)で D3O を使っている例が多い。HYODなどのメーカー |
komineのエニグマシリーズは瞬間的に硬くなるわけではないのですがCE2規格をクリアしている物もありますのでこちらも候補としても良いで良いですね。
普通のジャケットを買って中身のパッドをCE1規格の物からCE2規格に変更して、安全性を上げるのも良いと思います。
夏用のジャケットは暑くなりがちなので、エアスルー型通気性の良いものにすると熱中症対策にもなりますので一考する価値はあるとは思います。
最後に事故によるプロテクターの有無によっての死亡確率を載せておきます。
| 致命傷主部位 | 割合(例:国土交通省 2013〜2022年平均) | 備考 |
| 頭部 | 約 40.8%(警視庁東京統計では 44.9%) | 最多。ヘルメット着用の重要性を裏付ける。 |
| 胸部 | 約 28.6% | 頭部に次いで多い。胸部プロテクター着用が致死率低下に寄与。 |
| 頭部+胸部合計 | 約 70% | 二輪車死亡事故の大部分がこの2部位に集中。 |
というように頭部と胸部が全体の70%という高い数字になっています。ちょっとした買い物でも気を抜かず運転するのはもちろんのことですが、万が一のことがあった時に自分の事を守れる物を身に着けて運転しましょう。
プロテクターをすることで死亡事故や重傷にいたる確率も減ると思います。事故をして使うことがないのが一番だと思いますが、なにかあった時の為に備えをするのは大事なことだと思います。